人材獲得競争が激化する中、採用費用の高騰や応募者の質の低下に頭を悩ませる企業が増えています。
大手求人サイトへの掲載料は基本プランでも数十万円、上位プランでは100万円以上になることもあり、毎回の採用に多額の予算を投下しなければならない状況です。それに、高いお金を払っても「応募者のミスマッチ」や「早期離職」に繋がっては意味がありません。では、企業はどうすればこの採用課題を解決できるのでしょうか。
求人サイトvs自社サイト:採用競争の主戦場を徹底比較
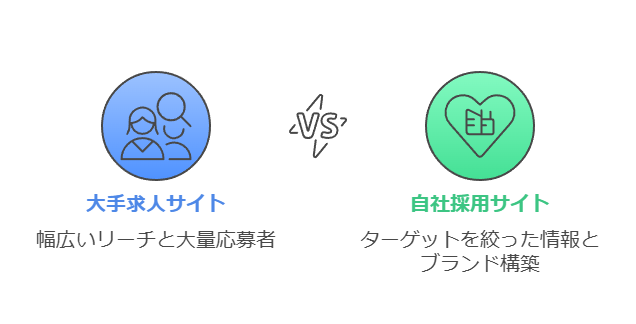
まず、求人サイト(求人情報プラットフォーム)と自社採用サイト(企業の採用ページ)の違いを押さえましょう。それぞれ役割や応募者心理、コスト面で特徴が異なります。
役割の違い:広く探すか、深く伝えるか
- 多数の企業情報を集約したプラットフォーム
- 幅広い求職者が対象
- 掲載情報に制限あり
- 「出会いの場」としての役割
- 大量応募者集めに適している
- 企業に特化した採用情報発信の場
- 興味がある求職者が対象
- 自由に情報発信できる
- 「口説き落とす場」としての役割
- 企業の魅力を深く伝えられる
大手求人サイトは多数の企業情報を集約したプラットフォームです。幅広い求職者が対象で、求人検索やスカウト機能を備えています。求職者にとっては多くの選択肢を比較検討できますし、企業にとっては大量の応募者集めに適しています。一方で掲載情報には制限があって、各社の魅力は限られた枠内でしか伝えられません。
自社採用サイトはその企業に特化した採用情報発信の場です。ターゲットは「その企業に興味がある求職者」であり、企業のビジョン・事業内容から社風、社員紹介まで自由に情報発信できます。例えば社内の写真や動画、社員インタビュー、1日の業務スケジュールなど、求人サイトのフォーマットでは載せきれないコンテンツも掲載可能です。
求人サイトが「出会いの場」だとすれば、自社採用サイトは「口説き落とす場」と言えるでしょう。企業の魅力を深く伝えて、応募したいと思わせる役割を担います。
応募者心理の違い:大量応募か、納得応募か
| 比較項目 | 大手求人サイト | 自社採用サイト |
|---|---|---|
| 応募者心理 | 「とりあえず受けてみよう」 軽い気持ちで応募するケースも | 「この会社で働きたい」 意欲が高い傾向 |
| コスト | 数十万円〜百万円単位 採用のたびに費用発生 | 初期投資は必要だが 長期的なROIに優れる |
| 情報量 | 限られたフォーマット内 | 無制限の情報発信が可能 |
大手求人サイト経由の応募者は、“とりあえず受けてみよう”という傾向があると言われます。興味はあっても、「合わなければ辞退すればいいや」という軽い気持ちで応募するケースも少なくありません。実際に採用担当者の悩みとして「選考辞退や内定辞退が多い」というのをよく聞きます。
一方、自社採用サイト経由の応募者は「その会社で働きたい」という意欲が高い傾向があります。サイトでじっくり企業研究した上で応募してくるから、最初から社風や仕事内容への理解が深いです。ビジョンや社員の声などを見て「この会社なら自分に合いそう」と納得してから応募するケースが多いので、安易な応募やミスマッチが減ります。つまり、求人サイトは量の確保に強みがありますが、自社サイトは質の面で優れているわけです。
コストとROIの比較:一見安価と感じる大量募集vs長期投資型の自社採用
正直、求人サイトのコストは高額です。大手求人媒体への掲載料は数十万円〜百万円単位になることも珍しくなく、採用できるか不確実なのに先行投資が必要で、新卒向けのナビサイトも基本プランだけで数十万円、追加オプションで100万円を超えるケースもあります。
中途向け求人サイトの成果報酬型だと、採用決定時に年収の何%かを支払う仕組みで、エージェント並みのコストがかかります。例えば転職エージェントの場合、年収500万円の人材を採用すると紹介手数料は約175万円(手数料率35%の場合)にもなります。求人サイトや人材紹介に依存する採用は、一人当たりの採用単価が高騰しやすいのが実態です。
一方、自社採用サイトのコストは初期投資こそ必要ですが、長期的に見ると費用対効果(ROI)に優れるとされています。自社サイトの制作には外注すれば数十万円〜100万円以上の費用がかかり、運用・更新にも社内リソース投入や多少の維持費が必要です。しかし、一度構築してしまえば求人掲載のたびに追加で多額の支払いをする必要はありません。自社サイト経由の応募獲得は基本的に成果課金なしで、応募が増えてもコストは増加しません。
【直接応募】採用サイトの圧倒的差別化ポイント
上記の比較から見えてくるように、自社採用サイトを中心とした直接応募は、求人サイトにはない差別化ポイントがあります。ここでは自社採用サイトのメリット・デメリットを整理しつつ、特に重要な「コンテンツ力」「コスト効率」、そして運用する際の課題について掘り下げます。
メリット・デメリット
- 採用コストの削減
- 採用ブランディング効果
- 採用データの蓄積
- 質の高い採用の実現
- サイト構築・運用の手間と費用
- 情報更新やコンテンツ制作のリソース
- サイト単体では応募集めが難しい
自社採用サイトのメリットは大きく3つあります。
第一に前述した採用コストの削減です。求人広告費や紹介手数料を大幅に圧縮できます。
第二に採用ブランディング効果です。自社サイトで企業文化や社員の声を発信することで、応募前からミスマッチを防げます。
第三に採用データの蓄積という観点も見逃せません。アクセス解析や応募者データのトラッキングができるので、採用プロセスの改善に役立ちます。「質の高い採用」を自社の力で実現できるのが強みだと思います。
一方デメリットもあります。
最大のハードルはサイト構築・運用の手間と費用です。自社にノウハウがなければ制作会社に依頼する必要があり、製作費だけで数十万〜100万円以上かかります。情報更新やコンテンツ制作にも時間とコストがかかり、社内リソースの確保が必要になります。
もう一つの課題は「自社サイト単体では応募を集めるのが難しい」こと。特に知名度が低い企業の場合、サイトを公開しただけでは求職者が訪れず、応募ゼロ…ということもあり得ます。なので自社採用サイトは他の集客施策と組み合わせる工夫が必要です。
コンテンツ力:企業の魅力を“伝え切る”情報発信
自社採用サイト最大の武器はコンテンツ発信です。求人サイトのフォーマットでは文字数や項目に制限がありますが、自社サイトなら制限なく発信できます。社員のインタビューや1日の仕事の流れ、写真や動画を駆使したオフィス紹介、社長メッセージや今後のビジョンなどのコンテンツで求職者の興味を引くことができます。
この自由度こそが、自社サイトによる“差別化”を生むポイントです。他社と比較検討している求職者に「この会社で働く具体的なイメージ」を想像させることで応募意欲を高められます。
コンテンツ力を発揮するには社内の協力が不可欠です。社員の声や写真を集めたり、記事を更新したりと手間はかかります。しかしその投資に見合うリターンは十分あると思います。自社採用サイトを活用して成功した企業の多くは、「自社のカルチャー発信」に力を入れています。
・社員インタビューや1日の仕事の流れ
・写真や動画を駆使したオフィス紹介
・社長メッセージや今後のビジョン
この自由度が、他社との差別化を生み出します
コスト面の優位性:広告費ゼロ採用への道
自社採用サイトは長期的なコスト削減効果が大きいです。初期構築や運用にはお金がかかりますが、採用広告や紹介会社への支払いと比べれば断然お得です。
さらに、自社サイト経由で採用した人材はミスマッチが少ないため早期離職が減り、中長期的には採用し直しによる余計なコストも削減できます。このような質的向上によるコスト削減効果も見逃せません。
総合すると、自社採用サイトは初期費用こそ必要なものの、一度軌道に乗せてしまえば「ランニングコストが低く、採用のたびに費用対効果が高まっていく」持続可能な仕組みだと思います。
・初期構築や運用にはお金がかかるが、広告費や紹介料と比べれば断然お得
・ミスマッチが少なく早期離職が減り、採用し直しのコストも削減
・ランニングコストが低く、採用のたびに費用対効果が高まる持続可能な仕組み
単独運用の課題:集客戦略と運用体制をどう確保するか
自社採用サイトのデメリットは「サイト単体で応募者を集めるのが難しい」という点です。特に知名度の低い中小企業やスタートアップの場合、求職者が自社名を検索してくれるとは限りません。サイトを公開しただけでは存在に気付かれないリスクがあります。
幸い、近年は求人検索エンジンやSNSを活用して自社採用サイトに誘導する手段が増えています。IndeedやGoogleしごと検索のような検索エンジンはウェブ上の求人情報を収集・表示してくれるので、自社サイトの求人情報も適切にマークアップすれば検索結果に表示されるようになります。
運用体制の面でも課題があります。自社採用サイトの成功には継続的な運用・改善が不可欠ですが、採用担当部門だけで全てを担うのは大変です。社員ブログ執筆やイベント情報発信に現場社員が参加する「社員巻き込み型採用広報」を取り入れる企業も増えていますね。採用サイト構築・運用を支援するATS(採用管理システム)や採用マーケティングツールを使えば、少人数でも効率良く回せると思います。
自社採用サイトは単独では応募者集めが難しいという課題があります。知名度の低い企業は求職者に見つけてもらえないリスクがあるため、他の集客施策と組み合わせる工夫が必要です。
求人サイトを使うメリット・デメリット
自社採用を強化するといっても、求人サイトを全く使わない方が良いというわけではありません。大手求人サイトにも独自のメリットがあり、上手に活用することで採用力を補完できます。ただし、デメリットも把握しておく必要があります。
メリット①:集客力とサポート体制による即戦力
求人サイト最大のメリットは圧倒的な集客力です。マイナビ転職やリクナビNEXT、dodaといった主要サイトには数百万規模の登録者がいて、求人を出せば短期間で多くの閲覧・応募が期待できます。自社名を知らない求職者にもリーチできるのは大きなメリット
また、多くの求人サイトでは専門の営業担当者やカスタマーサクセスが付き、原稿作成のアドバイスや効果測定レポートの提供などサポートも充実しています。
さらに、求人サイトによってはスカウト機能やレコメンド機能が利用できる点も見逃せません。企業側からデータベース上の候補者にアプローチできるスカウトメールは、能動的な採用アプローチ手段として便利です。自社採用サイトでは基本的に待ちの姿勢ですが、求人サイトのスカウトを使えば「求職者にこちらからアプローチできる」ので、採用の主導権を握りやすくなります。
- 圧倒的な集客力 – 主要サイトには数百万規模の登録者
- 専門の営業担当者やカスタマーサクセスのサポート
- スカウト機能やレコメンド機能による能動的採用アプローチ
メリット②:多様な求職者との接点と企業PR効果
求人サイトには日々たくさんの求職者が訪れます。そのため、自社の存在を知ってもらうきっかけ作りとしても有用です。特に知名度の低い企業にとって、求人サイトで募集を出すこと自体が一種の広告塔になります。
求人票には事業内容や仕事内容の概要が載るので、それを読んだ求職者が興味を持ち企業名で検索して自社採用サイトを訪れる、という流れも期待できます。求人サイトで自社を知った人が、そのまま採用ページに流入して詳細を確認するケースがあるということです。
- 求人サイトは自社の存在を知ってもらうきっかけになります。特に知名度の低い企業にとって、求人サイトへの掲載自体が一種の広告塔になります。
- 求人票を読んだ求職者が興味を持ち、企業名で検索して自社採用サイトを訪れる流れも期待できます。
デメリット:高コストと情報発信の制約
反対に、求人サイト利用のデメリットは主にコスト面にあります。先述のように、掲載料金や成功報酬など金銭的コストが大きく、予算を圧迫しがちです。
外部媒体への支出を積み重ねるほど、自社にノウハウや資産が蓄積されないまま費用だけ消えていく構造になってしまいます。加えて、求人サイト経由の応募者は動機が浅いこともあり、採用効率が低くなるリスクもあります。大量の応募者対応に工数を取られ、人事担当者の負担が増大することだってあります。
情報発信の自由度が低い点もデメリットです。求人サイト上の求人票ではフォーマットが決まっており、文字数や項目に限りがあります。求職者から見れば、どの会社も似たり寄ったりに見えてしまう恐れがあります。
デメリット
掲載料金や成功報酬など金銭的コストが大きく、予算を圧迫します。
外部媒体への支出は自社のノウハウや資産の蓄積につながりません。
また、求人サイト上のフォーマットでは情報発信の自由度が低いため、差別化が難しいです。
未来の採用戦略
ここまで見てきたように、大手求人サイトと自社採用サイトには一長一短があります。では、これからの企業はどのような採用戦略を描くべきなのでしょうか。
データ活用:採用を科学する時代へ
これからの採用活動では、感覚や勘だけでなくデータに基づく意思決定が重要になると思います。自社採用サイトはそのための基盤として最適です。サイトへのアクセスログやエントリー数の推移、ページ滞在時間など、あらゆる採用関連データを自社で蓄積・分析できるからです。
さらに、近年はAIやHRテックの発展により、応募者データの分析・活用はより高度になっています。応募者のスキルマッチ度をスコアリングしたり、内定承諾率を予測したりするサービスも登場しています。自社採用サイトとATSを連携させ、応募〜入社までのデータを一元管理すれば、「こういう志向の人は定着しやすい」「この経路から来た応募者は辞退率が高い」といった分析も可能になるでしょう。
これからの採用活動では、感覚や勘だけでなくデータに基づく意思決定が重要です。自社採用サイトは採用関連データの蓄積・分析の基盤として最適です。
- サイトへのアクセスログやエントリー数の推移
- ページ滞在時間などの分析
- AIやHRテックを活用した高度な応募者分析
ブランディングとダイレクトリクルーティング(DR)の融合
従来の求人広告型の採用が限界を迎える中、注目したいのがダイレクトリクルーティング(DR)という手法です。DRとは、企業自らが候補者に直接アプローチして口説く採用手法のことで、ビズリーチやWantedlyなどの登場で広まりました。今後はこのDRを自社のブランディング戦略と一体化して進めることがポイントになります。
具体的には、自社採用サイトやブログでファンを増やしつつ、同時に社員や採用担当者が直接有望人材にアプローチするという二段構えです。自社サイトの情報発信で企業の認知を広げ、共感した人材に対して、SNSやスカウトで直接アプローチしていきます。これなら、待ちの採用では出会えなかった層を開拓できますし、自社の価値観に合った人材をピンポイントで獲得しやすくなります。
今後の採用市場では、単に求人を出して待つだけでは優秀な人材は獲得困難になるでしょう。むしろ企業側から働きかけ、攻めの採用にシフトしていく必要があります。
従来の求人広告型採用から、ダイレクトリクルーティング(DR)へのシフトが進んでいます。
- 自社サイトやブログでファンを増やす
- 社員や採用担当者が直接有望人材にアプローチ
- 自社の価値観に合った人材をピンポイントで獲得
使い分け戦略
最後に、求人サイトと自社採用サイトの上手な使い分けについて考えてみます。結論から言えば、「どちらか一方」ではなく両者を適材適所で使い分けるハイブリッド戦略が有効です。
例えば、認知度向上や急募ポジションでは求人サイトを活用しつつ、企業理解を深め志望度を高める役割を自社採用サイトが担う、といった分業体制です。
求人サイト経由で応募した求職者にも必ず自社採用ページを案内し、選考中に企業理解を深めてもらう工夫をしている企業は少なくありません。求人サイトは入口、自社サイトは決め手という位置づけで使い分けると効果的です。
職種や採用ターゲットによって使い分ける方法もあります。新卒採用では知名度確保のためナビサイトを利用しつつ、説明会予約や社員紹介コンテンツは自社サイトで提供する。中途採用で専門スキル人材を探す場合はダイレクトリクルーティングサービスと自社サイトを組み合わせる、といった具合です。採用ポートフォリオを多様化しつつ自社サイトで一本化して受け入れるイメージです
求人サイトと自社採用サイトを適材適所で使い分けるハイブリッド戦略が有効です。
- 認知度向上や急募:求人サイト活用
- 企業理解を深め志望度を高める:自社サイト
- 求人サイトは入口、自社サイトは決め手
- 職種や採用ターゲットによる使い分け
まとめ
採用市場の変化に対応し、優秀な人材を獲得するには、ただ大手求人サイトに広告を出すだけじゃ足りません。コストをかけて母集団を集める従来型の採用手法に加え、自社採用サイトを軸にした「攻めの採用戦略」へと切り替えていく必要があると感じます。
「採用ページ制作プラン」で、貴社の魅力を最大限に発信しませんか?
本記事では、採用サイトの重要性や最新のトレンドについてご紹介しました。
企業が優秀な人材を獲得するためには、自社の魅力をしっかりと伝えられる採用サイトの存在が欠かせません。
私たちホームページ制作ZIUSでは、採用ページに特化した制作サービス「採用ページ制作プラン」をご用意しています。採用サイトに必要な、基本的な情報からデザイン・画像のご提供まで、貴社の採用活動を強力にサポート。
修正や更新のご依頼も、月額料金範囲内で対応可能ですので、まずはご相談ください。
また、LP形式のデザインなので、求職者が求める情報にすぐ辿り着くことができます。採用サイトの制作をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。


