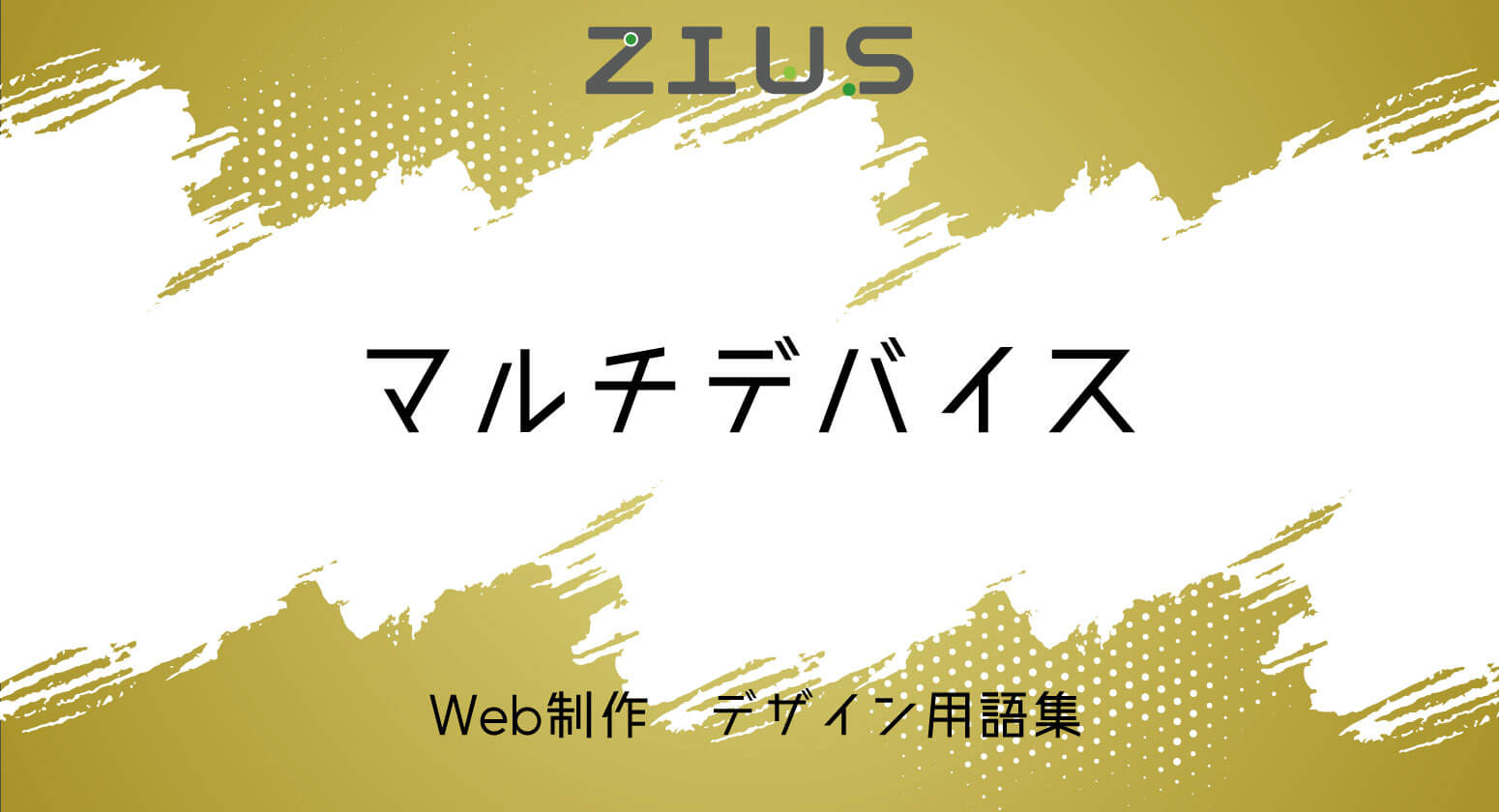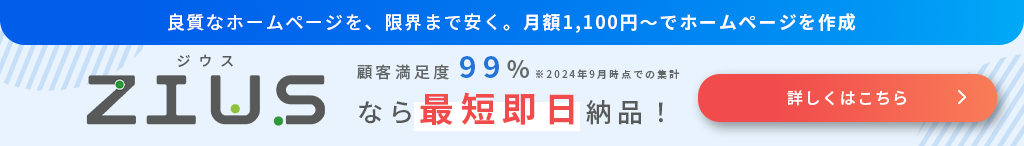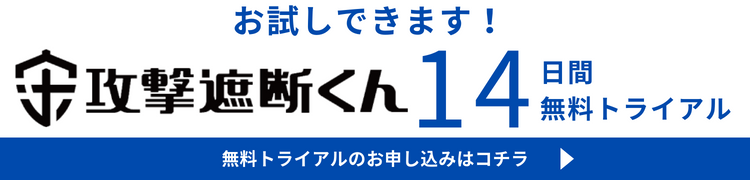この記事の目的
Webの世界は日進月歩で進化していて、便利で新しい技術がどんどん登場しています。
その進化に伴い、新たな用語も年々増えています。
私たちが提供する「ホームページ制作サービス」の観点から専門用語を抜粋して分かりやすくお伝えします。
この記事の対象読者
Web制作を始めたばかりの人。
Webデザインを行なっているが、言葉の定義を再確認したい人。
自社でWeb担当を任されたが専門用語についていろいろ知りたい人。
など、Webに限らずDXに携わるすべての方に。
マルチデバイスとは
サービスやコンテンツ、アプリケーションソフトなどを、さまざまな端末で共有して利用できることです。
例えば、コンテンツ配信サービスで購入したコンテンツを、スマートフォン・タブレット・コンピューターゲームで連携して利用できることなどを指します。
マルチデバイス化が求められる対象
コーポレートサイトだけではなく、業務系アプリ、ユーティリティアプリの他、BtoBにおいてはチャットアプリや営業販促ツールまで、現代ではどの領域においてもマルチデバイス化が求められます。
モバイルでの利用をメインとし、スマホ一つで制作・投稿・ソーシャルネットワークなどの基本的な性能や機能は搭載しているアプリが既に多く登場しており、日本では有名なものにTikTokやInstagramなどがあります。
しかしながら画像や動画制作などのクリエイティブ系サービスでは、プロレベルの高品質な作品作りにはまだまだマルチデバイス化は厳しいかもしれません。

マルチデバイス対応のWebサイト構築方法
画面サイズやブラウザなど想定されるユーザーの利用状況は十人十色です。
対策方法としては2種類あります。
- 端末ごと、OSごとに最適なWebページを用意
Webサーバー側でhttpプロトコルのユーザーエージェント情報を判別し、適切なページを表示させる方法です。
- レスポンシブコーディングをする
閲覧している画面サイズに合わせてサイズ変更させ、メディアクエリの記述をする。デバイスサイズごとのCSSの記述が必要になります。
このレスポンシブデザインはGoogleにも推奨されている方法です。
セキュリティ対策
複数の端末からアクセスできるようになると、ウイルス対策などのセキュリティ対策も欠かせなくなります。他には、下記のような項目についても対策しないといけません。
・怪しいアプリなどが入っていないか
・通信の盗聴対策
・デバイスの紛失・盗難対策
・ネットワークの脆弱性(無料Wi-Fi)対策
・モバイル用セキュリティアプリ導入
簡単に持ち運べないデスクトップPCと違い、どこにでも移動可能な端末だと、BtoBサービスの場合、情報へのアクセスを制限する必要があります。マルチデバイスに適したセキュリティアプリなどもあり、ヒューマンエラーに起因する問題以外はシステマティックに制限するべきでしょう。
スマホ端末での利用を想定しているサービスでも、ユーザーが何らかの事情でスマホからの操作ができない状況に遭ったとき、タブレットやPCからもアクセスでき同じ操作が出来ることが望ましいです。
WebサイトやWebサーバを守るクラウド型WAF 導入実績NO.1
常に進化する脅威に対応するためのセキュリティ対策は必須です。そこで提案したいのが『攻撃遮断くん』です。『攻撃遮断くん』をオススメする理由は3つあります。
- 高セキュリティ:自動更新される防御パターンにより、新たな脅威に即座に対応。
- 継続率98%以上:高品質なサービスと丁寧な顧客対応により、高い顧客満足度を実現。
- 純国産WAF:開発から運用、保守、サポートまでを一貫して国内で提供。
ニーズに応じた2タイプ(SaaS型、クラウド連携型)をご提供、さらにサイバー攻撃を可視化できます。
いまなら14日間の無料トライアル実施中。詳細はこちらをご確認ください。